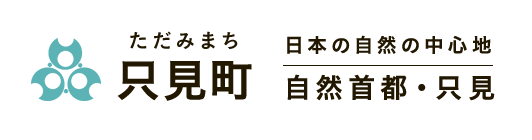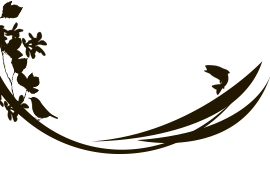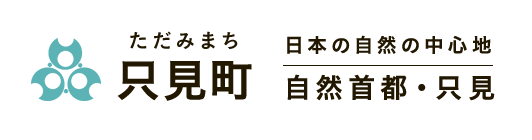森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税は法令により使途が定めらてれおり、市町村においては森林整備に関する施策や、森林整備を担うべき人材の及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進その他の森林整備の促進に関する施策に対する費用に充てることとされています。
税の概要
森林環境税について
・開始時期 令和6年度から
・税額 1,000円/年
・課税対象 個人住民税均等割課税対象者
・徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収
森林環境譲与税について
・開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
・譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し譲与
活用方針
只見町では、森林整備に関する施策及び森林の有する公益的機能の普及啓発並びに木材利用の促進等に関する施策に活用するとしており、下記のような事業への活用を想定しております。
| 項目 | 事業例 |
|---|
| 森林整備 |
・災害防止、レクレーションの場、景観形成等の森林整備等に取り組む各種事業
・森林経営管理制度に取り組む各種事業
・森林の間伐・除伐等による鳥獣被害防止対策に取り組む各種事業 |
| 人材育成・担い手確保 |
・技術研修など人材の育成と担い手確保等に取り組む各種事業 |
| 木材利用の促進 |
・建築物や木製製品及び間伐材などの利用促進など木材利用の促進に取り組む各種事業 |
| 普及啓発 |
・森林環境教育、植樹等に関する活動などの普及啓発に取り組む各種事業 |
| その他 |
・その他事業に必要な基金の造成、法令に定める使途に取り組む各種事業 |
森林環境税の使途について
森林経営管理制度について
森林環境税について
福島県では、水源のかん養や県土の保全など、私たちの生活にさまざまな恵みをもたらす森林の公益的機能の重要性を踏まえ、県民全体で森林を守り育て、本県の豊かな自然環境や良好な生活環境を将来にわたって維持し、次の世代に引き継いでいくための財源として、平成18年4月から森林環境税を導入しました。
- 税の仕組み
- 森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただきます。
- 納める人
- 納める額
- 個人: 1,000円/年
- 個人住民税(県民税+町民税)均等割は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から平成35年度までの10年間、500円を加算して納めていただきます。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
| 住民税均等割 | 標準税率 | 復興加算 | 森林環境税 | 合計 |
|---|
| 県民税 |
1,000円 |
500円 |
1,000円 |
2,500円 |
| 町民税 |
3,000円 |
500円 |
|
3,500円 |
| 合計 |
4,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
6,000円 |
- 法人: 法人県民税均等割の10パーセント相当額
| 区分(資本金等の額) | 森林環境税 |
|---|
| 50億円を超える法人 |
80,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
54,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
13,000円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 |
5,000円 |
| 上記の法人以外の法人等 |
2,000円 |
- 使いみち
- 森林環境の適正な保全
- 森林資源の利用促進
- 県民参画の推進
- 市町村が行う森林づくりの推進 など
- 令和5年度の実績
-
-
- 森林環境交付金(基本枠)
| 予算区分 | 支出済額 | 財源内訳 |
|---|
| 森林環境交付金 | 一般財源 |
|---|
| 県民参画の推進事業計 |
797,210円 |
600,000円 |
197,210円 |
|
企画展ポスター等印刷 |
797,210円 |
600,000円 |
197,210円 |
| 森林の適正管理推進事業計 |
396,000円 |
396,000円 |
0円 |
|
森林GISシステム運用支援委託 |
396,000円 |
396,000円 |
0円 |
| 森林環境学習の推進事業計 |
312,055円 |
250,000円 |
62,055円 |
|
只見小学校 |
69,624円 |
50,000円 |
19,624円 |
| 朝日小学校 |
24,200円 |
20,000円 |
4,200円 |
| 明和小学校 |
128,201円 |
100,000円 |
28,201円 |
| 只見中学校 |
90,030円 |
80,000円 |
10,030円 |
| 森林整備の推進事業計 |
6,369,000円 |
5,872,000円 |
497,000円 |
|
除伐、危険木伐採 |
6,369,000円 |
5,872,000円 |
497,000円 |
| 森林環境交付金基本枠計 |
7,874,265円 |
7,118,000円 |
756,265円 |
只見町森林整備計画
只見町森林整備計画について
只見町鳥獣被害防止計画
只見町鳥獣被害防止計画について
山菜・野生きのこ・野生樹実類の出荷制限について
福島県では、山菜やたけのこ等15品目、野生きのこ45品目及び野生樹実類3品目について、品目毎に放射性物質のモニタリグ検査を行っております。
昨年度までの検査の結果、食品中の基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが確認された市町村については引き続き出荷制限となっておりますので、出荷・販売を差し控えるようお願いします。加工品の原材料としても使用することができませんのでご注意ください。
なお、只見町では、下記の品目が出荷制限となっております。出荷、販売の際は出荷制限品目を受け入れないようにしてください。
出荷制限となっていない品目の出荷・販売については、発生初期にモニタリング検査を行い、安全性を確認してから出荷・販売をしてください。速やかに検査を実施するため、モニタリング検査の検体提供にご協力をお願いします。
自家消費野菜等の検査も受け付けております。詳しくは町担当部署までお問合せください。
- 出荷制限品目
- 山菜
こしあぶら(野生のものに限る)
- 野生きのこ類
すべての野生きのこ類(モニタリング検査の対象品目を除く)
- モニタリング検査対象品目
- 山菜
ぜんまい、たらのめ、わらび、たけのこ(真竹、淡竹など)、うど、うわばみそう(みず)、おおばぎぼうし(うるい)、くさそてつ(こごみ)、さんしょうの葉、ねまがりたけ、ふき、ふきのとう、もみじがさ(しどけ)
- 野生きのこ類
ならたけ、ぶなはりたけ、なめこ、むきたけ、くりたけ、まいたけ、まつたけ
- 樹実類
あけび、くるみ、とちのみ
- 問合せ先
- 南会津農林事務所 森林林業部林業課(電話 0241-62-5375)
森林法に基づく伐採届、林地開発等について
- 【林地開発許可申請】
- 地域森林計画の対象となっている民有林において土地の面積が1ヘクタール(利用目的が太陽光発電設備の設置にあっては、0.5ヘクタール)を超える開発行為をしようとするときは、次の場合を除き、都道府県知事の許可を受けることが法律で義務づけられています。(森林法第10条の2)
- (1) 国又は地方公共団体が行なう場合
- (2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
- (3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業の施行として行なう場合
- 【伐採及び伐採後の造林の届出】
- 市町村森林整備計画に従った適切な施業をするため、森林所有者や立木を買い受けた者などが立木を伐採するときは、次の場合を除き、伐採を始める30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を伐採する森林がある市町村の長へ提出することが法律で義務づけられています。(森林法第10条の8)
- (1) 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
- (2) 開発行為の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
- (3) 公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
- (4) 森林経営計画において定められている伐採をする場合
- (5) 森林所有者等が森林施業に関する測量又は実地調査のための許可を受けて伐採する場合
- (6) 立入調査等のための測量又は実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採する場合
- (7) 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林以外の森林であって、立木の果実の採取、樹液、樹皮又は葉の採取に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
- (8) 普通林であって、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき森林の面積が1ヘクタールを超えない範囲で指定したものにつき伐採する場合
- (9) 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- (10) 除伐する場合
- (11) その他農林水産省令で定める場合
- ① 保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
- ② 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
- ③ 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- ④ こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
- 届出をしないときは、100万円以下の罰金に処せられることがあります。(森林法第208条)
- ※保安林の場合は、この伐採及び伐採後の造林の届出によらず、福島県に届出等の手続きが必要になります。
- ※伐採及び伐採後の造林の届出において、「伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途」欄に記載する場合は、小規模林地開発に該当することから、小規模林地開発計画書を提出していただくこととなります。
- 只見町小規模林地開発取扱要綱.pdf・様式.doc
- ・伐採しようとするとき(伐採の始期の30日~90日前)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書.docx 伐採届記載要領・記載例.pdf
- 【添付書類】
- 〇森林の位置図及び区域図
- 〇届出者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書(国税庁法人番号公表サイトからの出力で代用可)
- 〇届出者が法人でない団体の場合は、代表者の氏名ならびに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
- 〇届出者が個人の場合は、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で氏名及び住所を証する書類
- 〇届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分(立木の伐採等に係る法規制一覧表)を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(記載例)
- 〇届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書、伐採後の造林に係る受委託契約書、土地の賃貸借契約書等で所在地番の確認できる書類【森林の土地の所有権(又は伐採後の造林をする権原)に関する状況を記載した書類(記載例)】
- 〇届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書等で当該森林を伐採する権限を有することを証する書類【伐採権原に関する状況を記載した書類(記載例)】
- 〇届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(記載例)【隣接森林所有者との境界確認に特別の事情がある場合の書類(記載例)】.pdf
- ※境界の確認を行ったことを証する書類は、次の場合は省略できます。
- ア 路網の作設や施設の保守等のため線上又は単木的な伐採を行う場合や、面的に伐採する場合で隣接する土地から距離をおいて伐採することを明らかにした場合
- イ 明確な谷や尾根により境界を判断できる場合や、立木への標示や林相により境界が明らかな場合(添付された区域図等から判断できない場合は現地写真添付必要)
- ・伐採した後(伐採の期間の末日から30日以内)
- ・造林した後(造林の期間の末日から30日以内)
- 【森林の土地の所有者届出】
- 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したときは、所有者となってから90日以内に「森林の土地の所有者届書」を取得した土地がある市町村の長へ提出することが法律で義務づけられています。(森林法第10条の7の2)
- 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内
- 届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。(森林法第213条)
木材の利用の促進について
・林野庁ホームページ
・只見町建築物等木材利用推進方針(PDF)
只見町薪ストーブ等普及支援事業補助金について
町内の森林資源の有効活用を促進し、森林環境の保全や森林の多面的機能の向上並びに低炭素社会の実現を図ることを目的とし、町内において薪を燃料として使用するストーブ又はボイラー(以下「薪ストーブ等」)を設置する方へ、補助を行います。
補助対象者及び要件
-
- ・町内に住所を有し、かつ居住している方、又は町内に事業所を有する方
- ・町税等を滞納していないこと
- ・当該補助金の交付申請を行った年度の3月末までに、設置及び費用の支払いを完了すること
- ・当該補助金の交付を、過去に一度も受けていない方
補助対象となる経費及び補助金の額
-
- ・薪ストーブ等本体(煙突を含む。)の購入及び設置にかかる経費(内装の不燃化工事を含む。)
- ・補助対象経費の2分の1以内とし、上限額は30万円
受付期間
-
- 令和7年4月25日(金曜日)から、予算額に達するまで。
- *土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分
申請の手続きについて
-
- 所定の様式を下記よりダウンロードいただき、郵送もしくは持参にて、下記まで提出してください。
- 提出先:只見町役場農林建設課農林係(町下庁舎1階)
-
- *補助金の交付を受けようとする方は、あらかじめ交付申請書の提出が必要です。
- *申請受付は先着順となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
補助金交付要綱
様式